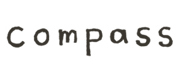LOOCHOO “TIME – LONDON meets OKINAWA. “
2012年4月26日〜30日、イギリスロンドンで開催
今回、ロンドンを拠点に活動している沖縄出身アーティス
会話:津波博美、平良亜弥 (2012年5月)
 博美: 去った4月のLOOCHOO展、Timeがテーマでしたが、亜弥さんはどういうTime/時を表現したかったのかな?
また、それをどうやってあらわしましたか?
博美: 去った4月のLOOCHOO展、Timeがテーマでしたが、亜弥さんはどういうTime/時を表現したかったのかな?
また、それをどうやってあらわしましたか?
亜弥: まず、作品の始まりの話になるんですけど。2~3年前くらいかな。蝉の羽化に興味があった時期がありました。末吉公園で、たくさんの蝉たちが夕暮れどきに土から出てきて羽化しているのを友人と眺めたりして、何か気になるなって。
ちょうど同じ時期、アパートの階段を上がっているとき、ふと壁をみると、
蝉が羽化しているところを発見しました。
どうしてこの蝉たちはわざわざコンクリートの壁で羽化するんだろうって
不思議に思って、その話を友人としてたら、
「もしかしてここは数年前は木が生えていたのかもしれないね」ってなって。
実際、アパートがいつできたのかはわからないのですが、、、。
蝉の抜け殻は「かつて」の象徴だなってそのとき思ったんです。 抜け殻は数年前のそこの環境も土の中も知っているだろうし、 羽化するために地上に出てきたとき、今の環境も知るから、 それら全部を記憶していたものの象徴に思えます。
何か、そうか考えると、抜け殻のパカッと割れた部分が宇宙みたいだなって。
宇宙から飛び去った蝉本体はどんな風に過ごしたのか。
それを考えるのも面白い。
もう蝉の抜け殻だけがぽんっとあるだけでも作品に思えてきて。
 蝉の抜け殻の中に時間を感じることで、
自分自身の中にも時間を感じるんです
。そうすると、存在しているすべてに時間が宿っているというかね。
個々として分かれているんじゃなくて、
時間を通して繋がっている感覚になるというか。
それで、今度は星座のように繋げたくりました。蝉の抜け殻をはじまりとして、
刺繍作品を点在させて、線で結んだ星座のような空間をつくろうと思ったんです。
星の輝きってひとつひとつだけど、それを人間は線でつないで星座にした。
作品の形については、そういう思考の流れがあったように思えます。
蝉の抜け殻の中に時間を感じることで、
自分自身の中にも時間を感じるんです
。そうすると、存在しているすべてに時間が宿っているというかね。
個々として分かれているんじゃなくて、
時間を通して繋がっている感覚になるというか。
それで、今度は星座のように繋げたくりました。蝉の抜け殻をはじまりとして、
刺繍作品を点在させて、線で結んだ星座のような空間をつくろうと思ったんです。
星の輝きってひとつひとつだけど、それを人間は線でつないで星座にした。
作品の形については、そういう思考の流れがあったように思えます。
博美: タイトルが、’空っぽの無限’ってあったけど、、、 無限のなかに、何か可能性があるとか?
亜弥: 逆です。 空っぽの中に可能性があるような感じがします。 空っぽの蝉の抜け殻の中に時間を見いだしたように、 空っぽのようにみえるけど、そこにはいろんな想像力の隙間があるかなって。 それで無限です。 無限の想像力でもって、繋がっているということを意識したかったのかもしれません。
博美: 無限の想像力がその空っぽの中にある。 なんだか、いろんなものがすごく詰まっている空っぽだね。刺繍を使ったのは?
亜弥: あぁ、難しい質問ですね。ん〜。。。刺繍してるときって何というか、やったことある人はわかると思うんですが、世界に入るんですよね。
空間を縫ったときと同じように、縫う作業の中でいろんなものを繋ぐ感覚に集中したいというか。できるというかね。星空、星座、宇宙を考えるとき私ができる作業の中で一番自然かな、と思って縫う作業を選びました。
博美: 刺繍のイメージがドローイングのような感じで私は好きでしたよ、それと布自体が宇宙になって、ドローイングが星のような、小宇宙が空間に散らばっているような。。
 沖縄から参加して、展示スペースが特に変わった場所だったけど、それに対してなにか苦労したとかありますか?
沖縄から参加して、展示スペースが特に変わった場所だったけど、それに対してなにか苦労したとかありますか?
亜弥:会場になったCrypt Galleryには今も500体以上の遺体が眠っていて、そういう場所にいる、展示する、というところはやっぱり緊張しました。 だから、星空を通したかったのかもしれません。
博美: どういうこと?
亜弥: 過ぎた時間との対話になるかなって。 展示のときに、刺繍が施されている布のパーツを 展示会場に散らして、それを糸で結んでたじゃないですか。 空間を縫っているとき、あの場所の時間を縫っているような気持ちが出てきて、ちょっとそこで一体になったというか。
博美: へーそうだったんだ
亜弥: そこであの場所でやることに挨拶できたというか。 やっぱり、あの場所はかなり変わった場所です。 特別な環境ですよね。 展示をするってだけじゃないというかね。 過ぎた時間と今ある時間を感じます。
博美: サイトスペシフィックな作品でもあったんだね。 (その場所の為の作品でもあったわけなんだ)
亜弥: そうですね。空間になじんで空気みたいな作品をつくりたいんです。 これまでうまくいっているのかは分からないのですが、、、。 空気を感じれるような空間をつくりたいです。 だから、作品という空間の中でぼーっとしている人をみるとよかったって思います。
博美: 反応はどうでしたか?
亜弥: ん~何人かと会話する機会がありましたが、一番良い反応を示していたのは、50代くらいのおじさんでした。 通訳を通してでしたが、刺繍の作品と2010年に「HOME/家」*で出した映像作品もゆっくりみてくれてたので、彼は何か感じてくれたのだと思いました。 あと、Guler Atesさん(現代美術家、映像作家/トルコ)。
博美: あー。「home/家」に参加した作家ね。
亜弥:彼女とは通訳がいなくて細かい話ができなかったのですが、 何かとても意見をしてくれていました。すごくそれが大事な言葉なような気がしていて。 彼女の話を聞きたかったです。 それと、今回、すごく良かったと思ったことがあって、
博美: おおおおおっ!何ですか?
亜弥: 「HOME/家」で出した作品を改めて自分自身でみなおしたときに、 あ、これ、好きだなぁって思えたことです。 自分の作品なのに。 刺繍の作品(新作)は、まだ処理できてなくて、 展示が始まってもモヤモヤしていましたが、 あの映像があることで、繋がった視点で生活していて、制作しているんだなって思いました。 だから、改めて前の作品を引っ張りだして展示するって結構重要なんだなって思ったんです。 ある程度眠らせる時間も必要なんですが。 そういうことを体験できたので、よかったです。
博美: 発見があったんだね。それは良かった!!!
作品たちにはもっとみられる権利があると思うよ。一度だけで終わるんじゃなくてね。
でもインスタレーションの作品って、結構儚いよね、そういう面で。とくにサイトスペシフィックな作品は。
亜弥さんが、そこで経験したこと、感じたことを聞けてすごくうれしいなー。
亜弥: 滞在中、Gulerさんとも話したかったです。
博美: そうだね、「Home/家」の作家達だけで会う時間もあれば良かったんだけど、、時間切れだったね。
博美: グループ展に関してどう思った?
亜弥:グループ展に関してはですね、デザイン、ファッションと、いろんな人たちとできてよかったです。 ただ、全体として”Timeを”表現する展示になっていたのかというのが気になります。 空間に救われているところがあったのかなぁって。
博美: 確かに、皆その一線で活躍している人だから、滅多に会わない人たちだったよね。 (”Timeを”を表現している展示かどうかについて)鋭いこというな。。。 たしかに空間に救われているのはどこかあると思う。 まあ、展示会場も展示のひとつだったかもね。 その空間じゃなくて、ホワイトキューブでみせたときに ”Timeを”を表現していたのかどうかっていうのがもっとはっきりしてくるのかな?
亜弥: そうですね、会場の情報を取り払っときにどうみえるのか、気になりますね。 博美さんとしてはどうでしたか?
博美: グループ展としてみたとき?
亜弥: 全体含めて。ちょっと感想聞きたいです。
博美: 来場者は楽しんで帰って行った展示会だったと思う。
やはりその一線で活躍している人たちの技術とかすごいと思ったしね。設置などテキパキしていて。アクシデントもありましたが、それをこなせる人たち。頼もしかったですね。
個人的には設置する時に一人一人の作家達と話会いながらできたらよかったんだけど、、もっと、見つめることができたんじゃないかなって、、、
もっと、会話しながら“Time”のこと、コンセプトを話し合いながら。
でも、亜弥さんの話を聞いて、そこの場所に挨拶するような感覚になっていったということを聞けて、多分、他の作家たちもそういう風な感覚になったなら、
一人で、黙々とやる時間瞑想的な時間も必要だったと思う。
実は私は泣いていたんだよ。。設置後、自分のスペースで。
私の作品はかなりダークなんですよ。
亜弥: 自分のスペースの中にいたら、もっと感情が出てくる感覚なんですか? それともそれらの感情を整える感じ?
博美: いえいえ、それが消えていたんです。
亜弥: よかった。 暖炉の前に集まる家族みたいな空間でしたもんね。
博美: 私の作品はアイディアがダークだったんです。 アイデアから、実際に作るまで時間があったから、 かなり私の中でそういう変な(ダークな)感情は薄れていって、 結局その場で作ったときに感謝の気持ちで一杯になって そこに眠っている人たちに「ありがとう」っていって、、泣いていました。
亜弥: それぞれの作家が自分の空間で何かしら空間とお話していたのかなって、今、博美さんの話を聞いて思いました。 他の作家たちの話を聞いてみたいですね。
博美: そうかもね。特に一人で作業していた人たちは。 あと、展示会で私のスペースが暖炉みたいとか、家族みたいとか、安心するとかいわれて、かなりびっくりしたよ。 そんなつもりで作ったわけではないのだけどね。。 だから、それが発見だったかな。
*「HOME/
2010年、沖縄で「HOME」をテーマに、沖縄又はイ
今回、LOOCHOO展でも12作品をイギリスで紹介し